
幼児音楽教育分野におけるセミナー講師派遣、講演の開催を承ります。
当社では、「子どもの表現を引き出すためのセミナー」と題し、幼児音楽教育に関する7種類のセミナーコンテンツをご用意しています。
ご予算、人数をお聞きしてご対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
担当講師
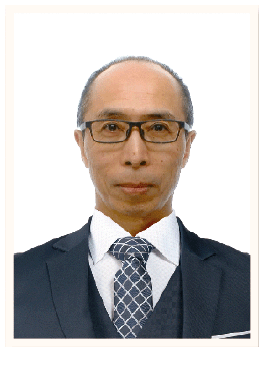
向阪芳弘
(有)プロデュースマツモト 営業部部長。
大阪芸術大学芸術学部音楽学科卒業。1980年より明浄学院高等学校芸術科音楽教諭として37年間勤務、2014年から教頭を務める。その後、大阪健康ほいく専門学校事務長を経て現職。
音楽理論ほか、ピアノ演習を多くの生徒へおこなう中で乳幼児期の音楽教育の重要性を了得、現在その大切さを広める活動を行っている。

坂本千鶴子
(有)プロデュースマツモト 教育部部長。
日本メディカル福祉専門学校こども福祉学科、湊川短期大学幼児教育保育学科、大阪青山大学子ども教育学科、姫路大学教育学部子ども未来学科通信教育課程などの専任、非常勤講師を経て現職。
1998 年より保育現場で実践している「リズムメロディ」リトミックプログラムの制作者。
ピアノのレッスンで関わった子どもの成長過程を客観的に見守られる立場から、著書「今、親が危ない」を著している。その他、(株)チャイルド社のDVD研修教材「10の姿と音楽教育」、オンライン研修教材「子どもの表現を引き出すリズムあそび」の講師を務める。

保育における音楽教育のあり方を探る
保育現場と音楽教育
音楽の定義にはじまり、現代における音楽の役割、そして私たちの国の普通教育が目指す方向性を、学習指導要領・保育所保育指針・幼稚園教育要領等の視点から、保育現場における音楽教育のあるべき姿を考えます。
■講演内容(90分)
1.音楽について(歴史と地域)
2.現代社会における音楽の役割
3.私たちの国における音楽教育
4.幼児教育における音楽教育プログラム
■講師メッセージ
音楽教育と言っても様々な形態があります。このセミナーでは音楽の英才教育ではなく、学齢に達するまでの全ての子ども達にふさわしい、園における音楽教育の姿を提示します。最初は音楽についての一般論から始め「音楽」に対する個々のイメージをリセットし、その後、セミナーの中核である私たちの国の普通教育が目指す方向性を、学習指導要領・保育所保育指針・幼稚園教育要領等の視点から再認識し、保育現場における音楽教育のあるべき姿を考えます。
そして最後に、この視点に立脚し、開催する各幼児教育音楽セミナーについてのご紹介をします。
■誌上講義 ~講演より一部抜粋~
園や学校における「音楽教育」を考えるにあったては、「音楽」のみに焦点を絞っていては、将来社会を担っていく発達段階の子どもたちを育成するという目的は達成されません。「学校教育」の目的と方向性をしっかりとまずは把握することが大切です。各領域・教科科目の役割は、それを実現するための手段であるわけです。

実践現場での子どもの心に届くピアノ伴奏を考える
子どもの表現を引き出す「ピアノ伴奏法」
子どもたちのその時々の状況や反応に対して、臨機応変に伴奏をすることができる生きた演奏法を、ピアノ教室でのレッスンとは違った観点から解説します。園に帰って今日から始められる簡単なポイントをお伝えします。
■講演内容(90分)
1.音楽の3要素
2.音楽の構成について
3.和音を理解するための基礎知識
4.練習課題(基礎)(応用)
5.伴奏型(基礎)(応用)
■講師メッセージ
保育の現場において、音楽はいろいろな場面で使用されます。音源としては、一つにCDや他の音楽データの利用がありますが、やはり生の楽器の演奏に勝るものはありません。そのためには保育士の楽器演奏能力の向上が必要です。しかし、ここで求められるものはミスのない楽譜通りの演奏能力ではありません。また、早い指の動きや難しい楽譜の演奏能力でもありません。必要なのは、たとえ伴奏譜がなくても、子どもたちのその時々の状況や反応に対して、臨機応変に伴奏をすることができる生きた演奏能力です。
当セミナーでは、感性を育むための音楽性と即興性を兼ね備えた「実用的」なピアノ伴奏の手がかりを、「コード」を中心に、ピアノ教室でのレッスンとは違った観点から解説をします。
■誌上講義 ~講演より一部抜粋~
項目ごとに1知識編と2実践編を織り交ぜて話を進めます。
ピアノあるいは電子キーボードがある場合は、それを使い説明の補足をします。
実践編においては、知識編で学んだ知識を演奏に結びつけるにはどのような練習をすればよいのか、実際の曲にどのように応用すればよいのかを学びます。
そして、実践編の終盤では、現場ですぐに活用できる伴奏型の例を幾つか示し、最後に、このセミナーで学んだ全ての知識と技法を全て使用した範例をあげ復習します。

0歳から5歳の生きる力を育む保育を考える
子どもの表現を引き出す「リズムあそび」
「生きる力」を育むために、子どもたちにとっての「リズムあそび」が、主体的・対話的な経験とどう結びつくのか、園で取り入れられるプログラムを紹介しながら解説します。
■講演内容(90分)
1.カリキュラムの実践にあたりなぜリズム遊びなのか
2.0歳児のリズムあそびから身体表現を引き出すには
3.0歳児から年齢に応じたステップのプログラムを理解
4.各年齢においてのプログラム内容でのピアノ伴奏 ほか
■講師メッセージ
保育所保育指針の改定において、保育所は「幼児教育施設」であると明記され、今まで以上に、養護と教育が一体となった保育を展開していくことが求められています。また、平成30年の保育所保育指針の改定では「小学校入学時以降の姿を視野に入れた保育を0歳の時期から行う」という姿勢が示されることとなりました。園生活での子どもたちが、就学前に「わかる」「できる」「おもしろい」と思える事を多く経験し、友だちと考え、友だちと協力し、友だちと達成感を味わうことが、子どもたちのアクティブ・ラーニングに繋がると信じています。
0歳児からの関わりが重要視されている今、リズムあそびはとても有用な音楽活動です。
■誌上講義 ~講演より一部抜粋~
園としての役わり
保育所保育指針の第2章の感性と表現に関する領域において、音楽やリズムに合わせて体を動かすという経験を通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにすることを求められています。2020年度より小学校から順次施行される「学習指導要領」の「音楽」の授業の歌唱と器楽の指導においても内容の充実が図られるようになりました。子どもたちが能動的(アクティブ)に学び続ける視点から、「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」を重視されます。「リズムあそび」での園の役わりも年齢別に示します。
保育者の役わり
教え込みではなく、子どもたち自身が音に触れ、体幹を鍛えながら伸び伸びと音と楽しむには、音楽活動にどう向き合うか?現場の先生は子どもたちにどう指導していくのか?
子どもの音楽活動表現を支える実践力を研究し、指導力を高めることが求められます。
保育者の願い
今回の「リズムあそび」が、主体的・対話的な経験として、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動できる「生きる力」を育み、自己表現力を礎に人生を切り拓いていく力になることを願っています。

保育現場での「遊び」を考える
子どもの表現を引き出す「手あそび」
子どもの発達段階に応じた手遊びの意義と必要性について、また、園で手遊びが行われる理由を、保育現場で人気が高い手遊び歌を紹介しながら解説します。
■講演内容(90分)
1.手遊びとは?
2.手遊びの意義と必要性について
3.こども園で手遊びが行われる理由
4.保育園で人気が高い手遊び歌
■講師メッセージ
みんなで歌に合わせて楽しく遊べるので、子どもたちも喜んで遊ぶことができる「手遊び歌」。歌が歌えない子どもでも、先生が歌いながらお手本を見せると、それを真似して遊べます。指や手を使う簡単なものから、全身を使って大きく動くものまで種類が豊富です。園では全身を使って大きく動かすこともありますが、ほとんどは指や手だけを使うので場所を取りません。場所を選ばず行える遊びとして保育に取り入れることが出来ます。
当セミナーでは、手遊びの意義や必要性について解説いたします。また実践編として実際に年齢別でどういった手遊びの導入をするのが良いか、丁寧に解説いたします。
今日からすぐに取り入れられる手遊びのポイントについてもお伝えします。
■誌上講義 ~講演より一部抜粋~
園としての「手遊び」とは
園では子どもたちが楽しく遊んで過ごします。いろんなことをして過ごしますが、その中に手遊びというのがあります。手遊びには子どもの成長に役立つ効果が期待できるので、多くの園で取り入れられています。今回手遊びにどんなメリットがあるのかを解説します。
手遊びの意義と必要性について
教育内容の中で最も多くの時間を費やすのは「遊び」の時間であり、身体的運動的発達を促す動きのある遊びや、人間関係のあり方や社会のルールを学習することができるような遊びが体験できる場として重視されています。これらには発達段階によるものや具体的な遊びがあり、それぞれの遊びに目的や効果を見出すことができます。
こども園で手遊びが行われる理由
園で手遊びを行うのは、子どもに人気があるからという以外にもいくつかの理由があります。なぜ園で手遊びを積極的に行っているのか、その理由を見ていきましょう。

保育に取り入れる音楽を考える
子どもの表現を引き出す「わらべうた」
「わらべうた」は民謡と同じく、私たちの国の長い歴史の中で育まれ、多くは子どもたちを中心に遊びの中で歌い継がれてきました。その背景から、今後の保育へ如何にして取り入れるのが良いか、実践例をもとにお伝えします。
■講演内容(90分)
1.わらべうたの歴史
2.わらべうたの意義と必要性について
3.わらべうたの種類に合わせた唄
4.わらべうたの唄に合わせた意味
5.わらべうたの実践 ほか
■講師メッセージ
保育所保育指針、幼稚園教育要領の「表現」の領域において、遊びを通して子どもの音楽表現を育む保育が求められています。また、小学校以降の「学習指導要領」における「音楽」の授業の「歌唱と器楽の指導」においては、伝統芸術音楽、民謡、唱歌、郷土に伝わる歌がさらに取り上げられ、内容の充実が図られるようになりました。
グローバル化が進む中、私たちが生まれ育ってきたこの国の歴史と伝統と文化をしっかり と継承していくことは、私たち自身のアイデンティティの確立のために必要な要素で、私たちの使命です。
■誌上講義 ~講演より一部抜粋~
昔から歌い継がれてきた「わらべうた」の力は、愛着関係を育み、聴く力を育 み、豊かな言語体験と音楽リズムの基礎を育むため、現代においても必要不可欠な子育ての内容であるために見直され、伝えられています。
知識編
・わらべうたの種類
・わらべうたの意義
実践編
・遊ばせ遊び唄
・遊びうた
・自然や動・植物に唄いかける唄
・年中行事の唄
・子守唄

集団行動による10の姿の[協同性]を考える
子どもの表現を引き出す「合奏」
保育所保育指針の第2章で求められる、子どもたちが音楽やリズムに合わせて、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする合奏。保育に合奏を取り入れる上での心得、準備から指導方法までを丁寧に解説します。
■講演内容(90分)
1.合奏の意義と必要性について
2.幼児期の終わりまでに育ってほしい『10の姿』
3.合奏を指導する側の心得
4.合奏の理念概念として
5.年齢別合奏指導法 ほか
■講師メッセージ
保育所保育指針の第2章の感性と表現に関する領域において、音楽やリズムに合わせて体を動かすという経験を通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにすることを求められています。2020年度より小学校から順次施行される「学習指導要領」の「音楽」の授業の歌唱と器楽の指導においては、内容の充実が図られるようになりました。子どもたちが能動的(アクティブ)に学び続ける視点から、「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」を重視されます。「幼児期の終わりまでに育ってほしい『10の姿』」にも反映したものとなっています。園生活での「合奏」はこれらの内容を獲得できる点からもとても有意であると考えます。
■誌上講義 ~講演より一部抜粋~
園としての「合奏」との関わり
園生活での子どもたちが、就学前に「わかる」「できる」「おもしろい」と思える事を多く経験し、友だちと考え、友だちと協力し、友だちと達成感を味わうことが、子どもたちのアクティブ・ラーニングに繋がると考えます。今回の合奏へのアプローチ方法が、主体的・対話的な経験として、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動できる「生きる力」を育み、人生を切り拓いていく力になると思っています。
合奏から得た心の成長を「10の姿」に紐付けをする
「幼児期の終わりまでに育ってほしい『10の姿』」全ての項目に紐付けできる心の成長があります。到達の喜びと充実感を得られる導きさえ忘れなければ、合奏は成長段階においても、貴重な役割を果たすことになります。

